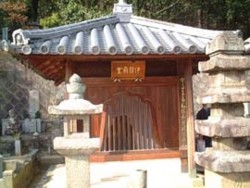表紙へ戻る
★伊勢寺(いせじ)
 乾性寺から、さらに坂を登ると伊勢寺が見えてきます。宇多天皇に愛された 歌人伊勢姫ゆかりのお寺です。
乾性寺から、さらに坂を登ると伊勢寺が見えてきます。宇多天皇に愛された 歌人伊勢姫ゆかりのお寺です。
伊勢姫の隠居所跡の草庵があったところを、後にあらためて寺院とし、伊勢寺と称したと言われて、金剛山象王窟(こんごうさん−しょうおうくつ)と号して曹洞宗に属し、聖観音を本尊とします。
天正年間(1573〜92)、高山右近の兵火で焼失したと伝えられますが、元和から寛永(1624〜44)の頃、宗永が再興し、この時に天台宗から曹洞宗に転じました。
寺宝に伊勢使用の古硯・古鏡などがあります。伊勢姫は三十六歌仙の一人で、藤原継陰の娘です。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
★ 伊勢廟堂(いせびょうどう)
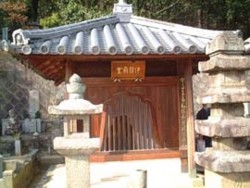
伊勢廟堂(いせびょうどう)は 本堂の西側にあり、碑は慶安4年(1651)、高槻城主の永井直清が建立しました。碑の文章は幕府の大学頭・儒学者林羅山 が書きました。直清は、その前年に能因法師を顕彰しており、能因が慕っていたという伊勢と寺名を結びつけた伝承をもとにして、これを顕彰したといわれています。
歌碑があり、
難波潟 みじかき葦の ふしの間も 逢はで この世を 過してよとや
と書いてあります。
百人一首でいつも聞いている歌ですが、伊勢姫が過ごした場所を訪れたことにより、また違った歌の印象を持つことが出来ると思います。
次へ
 乾性寺から、さらに坂を登ると伊勢寺が見えてきます。宇多天皇に愛された 歌人伊勢姫ゆかりのお寺です。
乾性寺から、さらに坂を登ると伊勢寺が見えてきます。宇多天皇に愛された 歌人伊勢姫ゆかりのお寺です。